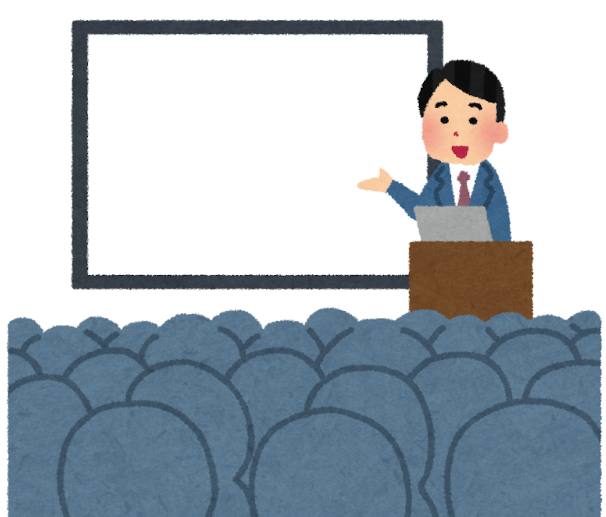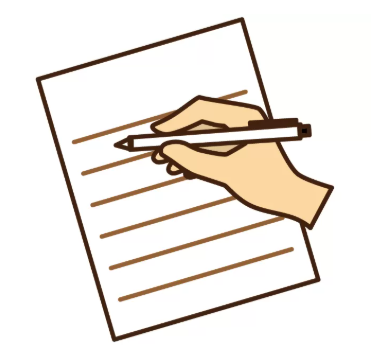民泊を始める前に知っておきたい法律って何?(初心者向け)
これから民泊を始めてみたいと考えている方にとって、「そもそも民泊って法律的に大丈夫なの?」「許可は必要なの?」という疑問はとても大きいものです。また、自身で民泊を調べても、一言で“民泊”と言ってもいろいろと種類があり、ややこしく感じられているかもしれません。
ここでは、民泊に関係する代表的な法律を初心者向けにわかりやすく解説し、具体的な民泊の例を交えてご紹介します。民泊の法律を知りたい方や、合法的に民泊を始めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
◼ 1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」は、2018年に施行された比較的新しい法律です。この制度では、年間180日まで自宅や空き家を使って宿泊サービスを提供することが可能になります。特徴としては、「許可制」ではなく「届出制」であること、自主管理が難しい場合は住宅宿泊管理業者の委託が必要なこと、また、消防設備や清掃体制の整備が義務付けられている点が挙げられます。
この制度は、自宅の一室を活用したい方や、空き家を収益化したい方に向いています。
具体例としては、「平日は東京で暮らしており、週末だけ大阪の実家に帰る」という方が、その空いている実家をAirbnbで貸し出すようなケースです。このような使い方なら、年間180日以内の制限の範囲で運営可能です。
◼ 2. 特区民泊制度とは?
特区民泊制度は、国家戦略特区に指定された地域でのみ利用できる民泊制度です。大阪市や東京都大田区などが対象地域となっており、こちらは年間営業日数の制限がないことが大きな特徴です。その代わり、制度利用には自治体ごとの条例に基づく「許可」が必要となります。一般的には、2泊3日以上の宿泊が義務づけられているケースが多いです。
本格的に民泊事業を行いたい方や、年間を通じて宿泊サービスを提供したい方には、この特区民泊制度が適しています。
たとえば、大阪市中央区の中古マンションを購入し、民泊用にリフォームして通年運営を行う場合、この特区民泊制度による「許可取得」が必要となります。
◼ 3. 旅館業法とは?
旅館業法は、もともとホテルや旅館、簡易宿所などの営業に適用されてきた法律です。民泊でも、施設の用途や運営形態によってはこの法律に基づいた許可が必要となります。旅館業法に基づく営業には、一定の構造・設備基準を満たす必要があり、たとえば廊下の幅、換気設備、トイレの数なども規定されています。
営業日数に制限はなく、365日営業可能ですが、申請や許可取得のハードルはやや高めです。
たとえば、古民家を全面改装して、訪日外国人観光客向けの一棟貸し宿泊施設として運営する場合には、この旅館業法による許可が必要になります。
◼ 4. その他に注意すべき法律やルール
民泊を運営する際には、上記の法律以外にもいくつか注意すべき関連規制があります。
たとえば、消防法では火災報知器や消火器などの設置が義務付けられており、物件の規模や間取りによっては追加の防火設備が必要です。また、建築基準法の用途地域によっては、民泊そのものが認められていない場所もあります。
マンションなど集合住宅では、分譲管理規約によって「民泊禁止」と定められているケースも多く、事前確認が不可欠です。さらに、賃貸物件の場合は、賃貸契約書に「転貸禁止」の条項が含まれていると、勝手に民泊に転用することは契約違反となります。
◼ 民泊を始める前にやるべきこと
まず、自分の物件で民泊ができるかどうかを調べましょう。これは用途地域の確認や、建物の管理規約、契約書の内容を確認することから始まります。次に、どの制度(民泊新法、特区民泊、旅館業法)に該当するかを見極めましょう。制度によって必要な手続きや条件が大きく異なります。
その後は、必要な書類や消防設備などの準備を進め、行政への届出や許可申請を行います。行政書士など専門家に相談すると、スムーズに進めることができます。
民泊を始めたいけれど法律がわかりにくいと感じている方は多いですが、基本をしっかり押さえて準備すれば、安全で合法的な民泊運営が可能です。疑問や不安がある場合は、是非当センターへご相談ください。